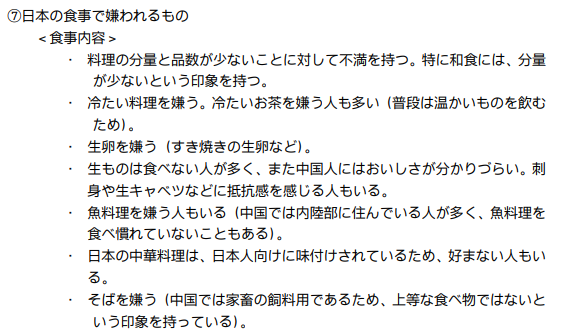毎年年末の恒例行事となっているHHKの紅白歌合戦を見て、初詣に行くという流れもかなり前から変わりつつあります。
- 紅白歌合戦、平成元年の「第40回」で終了するはずだった(外部サイト)
- 米津玄師、あいみょん、スピッツ 「紅白出場辞退」の真相(外部サイト)
令和初となる紅白歌合戦のため、NHKも気合が入っているようですが、テレビ離れも進んでいます。
若い世代でテレビ離れ進む 約1割「見ていない」―時事世論調査(外部サイト)
紅白歌合戦は必要なのかどうか、また今後紅白歌合戦をはじめとしてNHKのコンテンツって必要なのかを考えてみます。
紅白歌合戦の必要性
1951年(昭和26年)に第1回を放送して、その後1989年(平成元年)に2部構成となって、平成30年まで続いています。
紅白歌合戦ヒストリー(外部サイト)
紅白歌合戦の歴史を見ようとしても、2つくらいしか見つけられませんでした。しかも一つはウィキペディア…。
- NHK紅白歌合戦(外部サイト)
- 年末年始はなぜ『紅白』?(外部サイト)
必要かどうかはわかりませんでしたが、皆さんの認識として年末といえば紅白歌合戦といえるくらい浸透しきっています。紅白歌合戦見ないと年末ではないという認識もあり、まだ多くの人にとっては必要と思います。
紅白歌合戦が今後生き残る方法
まだ紅白歌合戦は必要だと結論出しましたが、紅白歌合戦が今後も必要かというと微妙です。こんな報告があります。
平成の紅白歌合戦 打ち切り説を乗り越えた挑戦の歴史(外部サイト)
2000年以降、視聴率が下がり始めています。それでも30%は超えていますが、最高視聴率の81.4%(1963年放送時)に近づくのは、娯楽の多様性からも難しいと言えます。
今は年末年始であっても仕事に従事している方も多く、テレビが強いと言っても娯楽は増えてきました。スマホ、YouTube、映画など多岐にわたる娯楽があり、年末年始も営業しているアミューズメントもあります。今までの娯楽がテレビに偏りすぎていたと言われて当然です。この流れから行くとテレビが従来の覇権を取ることはできないです。
生き残る方法としては、新しい娯楽と更なる相乗効果を狙うしかないと思います。一番良いと思うのが、オンデマンド放送の料金をNHK受信料に含めるもしくはオンデマンド放送を契約する人はNHK受信料を相当額値引くです。
NHKの番組もよいものはたくさんあるので、便利に使いやすくなってほしいです。
まとめ
いろいろ言いましたが、紅白歌合戦だけではなく、テレビコンテンツのことを考えると以下が改善した方が良い点と思います。
- 紅白歌合戦も含めて公共性・公平性の高い重要コンテンツが多いため、必要性はある。今後もNHKだから作れると言われるコンテンツを作ってほしい
- テレビ受信料とオンデマンド料金は統合した方が利用者の納得感が得られる
- 放送法が問題というのであれば、NHKから国民目線で放送法の改正を提案するべき